こんにちは!
ミニバスのリアルを発信するブログ管理人です。
バスケは仲間と一緒に成長できる
素晴らしい環境
 「うちのチームはみんな仲がいいんです!」
「うちのチームはみんな仲がいいんです!」
というのは、よく聞く美談のひとつです。
しかし…
「仲良し=強いチーム」とは限らないという
現実、知っていますか?
今回は、実際によくある「仲良しすぎるチームが陥りがちな落とし穴」とその末路について
現場目線でお届けします。
バスケ練習用のボールはこちら!
↓ ↓ ↓ ↓
|
|
Contents
ライバル心ゼロで練習に緊張感がない

「競争よりも仲良く」が前面に出すぎて
お互いを遠慮し合い、全力を出さなくなる
ケースがあります。
例えばシュート練習でミスしても
誰も何も言わない。
1on1で手を抜いても笑って終わる。
仲がいいのはいいことだけど
練習の中に“張り合い”がなければ
技術は伸びないのが現実です
“空気を読む”ことが優先され、指導が通らない

コーチが「もっと強気でいこう!」
と指示しても
「でも○○ちゃんが控えめだから、自分も…」
と空気を優先
この“仲良しの同調圧力”が
プレーの積極性を奪ってしまうんです
チーム内の雰囲気が良いのに
いざ試合になるとガンガン攻められない
「うちの子、練習では良いのに
試合で消極的なんです…」
という相談の裏には
こうした空気感が影響していることもあります
レギュラー争いが“気まずさ”に変わる
誰かがスタメンに選ばれると
周りの子や保護者がザワザワ…。
「仲良しだったのに」
「うちの子だけ出番が少ない」など、
レギュラー争いが友情の崩壊につながる
ケースも珍しくありません
コーチとしては実力や成長度を見て
判断していても、
“仲良しフィルター”
がその判断を歪めてしまうのです。
最後は“仲良し”だけが残り、勝負から遠ざかる
競争のないぬるま湯状態に慣れたチームは、やがてこうなります。
- 厳しい練習に耐えられず離脱者が増える
- 負けても「まあいいか」の空気
- 強くなりたい子が他チームに移籍する
残ったのは「仲良しなメンバー」だけ
でも、勝てない・成長できないチームになってしまったという残念なケースも、実際に多く見られます。
まとめ:仲の良さと競争心は“両立”できる
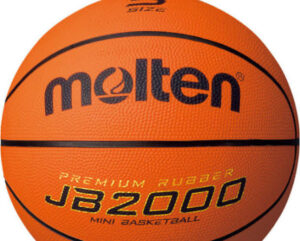
誤解しないでください。
仲が良いこと自体は素晴らしいことです。
でも、
「バスケは勝負の世界」
競争を恐れず
切磋琢磨できる関係こそ
真の仲間だと私は思います。
「勝ちたい」「うまくなりたい」という気持ちを、お互いが認め合うチームづくりが大切です。
子どもたちの未来のためにも、“仲良し”と“真剣勝負”のバランスを見直してみませんか?
ライバルと差をつけたいならコチラ
バスケットシューズ
↓ ↓ ↓ ↓ ↓
|
|
次回の記事では、「仲良しチームを強くするコーチング術」について深掘りしていきます!


