ミニバスコーチとしての2年間は、想像を超える「試練」と「学び」に満ちていました。
最初から私たちは実力主義を掲げ、年齢や学年に関係なく、努力と成長を見せた子が試合に出る方針でチームを運営していました。
しかし、その方針が一部の保護者との対立を生み、現場は次第に苦しい状況へとなっていきました。
狂い始めた瞬間

ある日、一部の保護者からこう言われました。
「6年生だけを試合に出してください」
最初から明確に伝えていた方針は「実力主義」それでも保護者の期待や希望は強く、
方針を理解してもらうことは簡単ではありませんでした。
とまらないクレーム
- 「なぜうちの子が出られないのか」
- 「6年生が優先されるべきだ」
- 「二部練をやらせたい」
練習内容、選手選考、試合の采配、戦術にいたるまで――あらゆる判断に対して不満が寄せられるようになりました。
中には保護者が子どもを誘導して「県で一番勝つチームになりたい」と言わせる場面もあり、親の期待がチームの空気を変えてしまうこともありました。
苦しくなる日々

次第に、私たちは保護者の顔色をうかがいながら指導をするようになっていきました。
本来大切にしていた「子どもたちの成長」を守る判断が、誤解や非難の対象にされる場面が増えたのです。
ある主力選手がケガで離脱した際、ベンチ入りを見送った判断に対して次のような言葉が返ってきました。
「どうせなら嫌いだから外した」
「かわいそうじゃないの?」
「ケガして落ち込んでいる子を外すなんて信じられない」
どんなに子どものためを思って決断しても、時にそれは悪意として受け取られてしまいます。
決断の保護者会

げんかいを感じた私たちは、保護者会を開きました。議題はシンプルです。
「このままコーチ陣が残るべきか、辞めるべきか。」
最終的に、多くの保護者から「残ってほしい」という支持があり、私たちはチームに残る決断をしました。
しかし一方で、一部の保護者は子どもを連れて退部していきました。
続くクレーム

退部後も、次のような連絡が続きました
- 「あなたたちのせいで辞めた」
- 「返金しろ」
- 「訴えたい」
精神的に辛い日々が続きましたが、私は今でもはっきりと言えます。
子どもたちの成長を第一に考えた指導は間違っていなかった。
まとめ

この2年間は、悔しさや葛藤に満ちていました。それでも、子どもたちが見せてくれた笑顔や成長が、私たちの支えでした。
勝つことは大事ですが、勝利だけが子どもの価値ではないという信念を忘れてはいけません。
もし今、同じように悩んでいるコーチがいるなら──
どうか、子どもたちの成長を優先してください
保護者のバスケではないのですから、
ほそく
この記事は、私がミニバスコーチとして過ごした実際の2年間をもとに書いています。
登場する人物やチーム名はすべて仮名です。
同じように悩む指導者・保護者の参考になれば幸いです。
迷ったら、まずこの一冊。
|
|
バスケのコーチング
|
|
(コメント欄での体験共有や、同じ立場の方からのアドバイスはいつでも歓迎します)
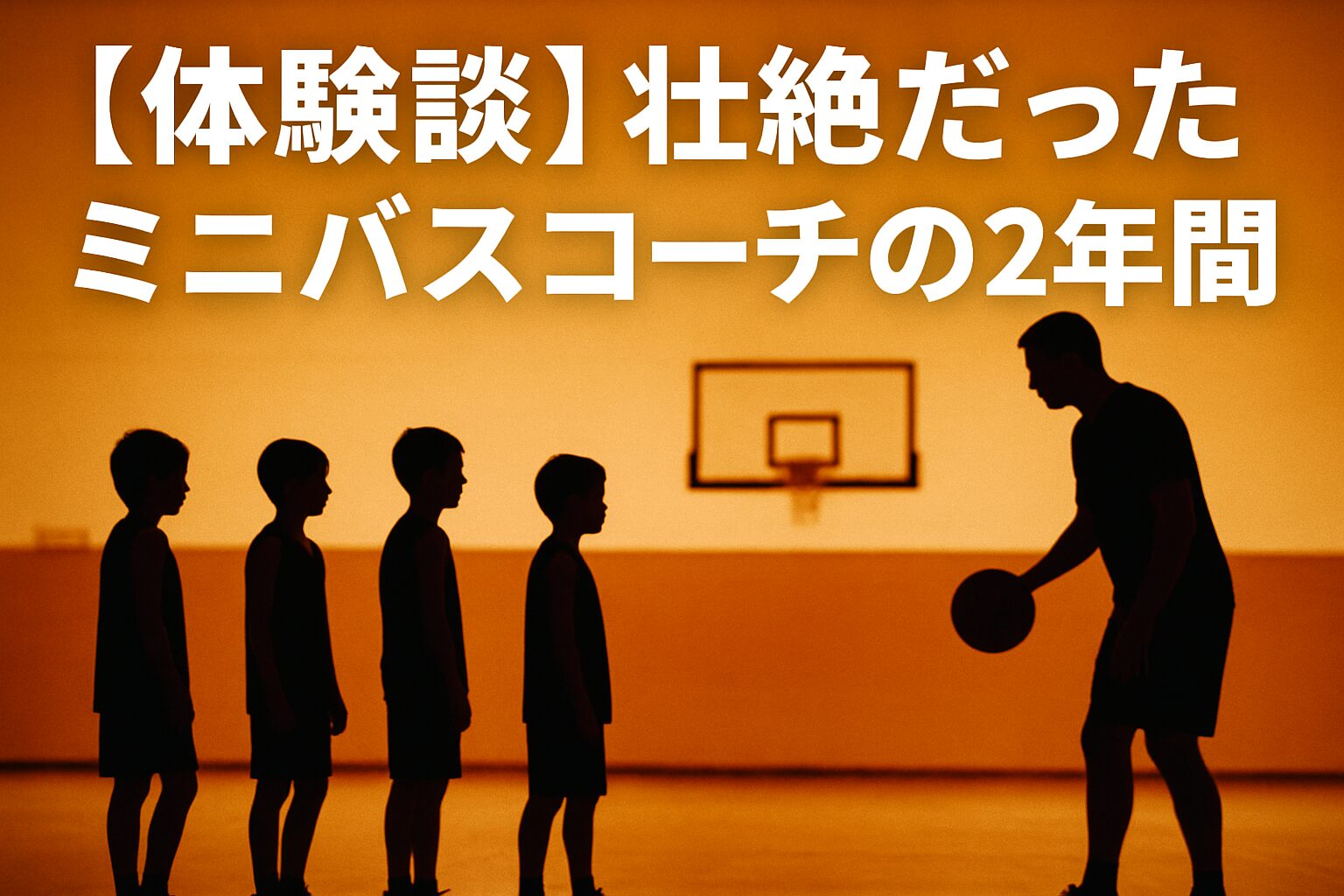
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/30e251bf.6451ce87.30e251c0.1e2defd3/?me_id=1213310&item_id=20270729&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fbook%2Fcabinet%2F3319%2F9784583113319.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)
![[商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。] [商品価格に関しましては、リンクが作成された時点と現時点で情報が変更されている場合がございます。]](https://hbb.afl.rakuten.co.jp/hgb/4801af72.76d7a9a5.4801af73.b90a50c0/?me_id=1338610&item_id=10000252&pc=https%3A%2F%2Fthumbnail.image.rakuten.co.jp%2F%400_mall%2Fporto3%2Fcabinet%2F09550308%2Fcompass1682352245.jpg%3F_ex%3D128x128&s=128x128&t=picttext)